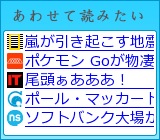2007年09月10日
上賀茂神社【重陽神事・烏相撲】
季節の節目というのは、誠に重要でこれまでにも上巳や七夕など有名な神事が御座いますが、特に重要とされているのが「重陽」といわれる九月九日で御座います。
陰陽の考えで、奇数は「陽」の数とされており、その中でも「九」という数字は陽の一番大きな数が重なることから「重陽」と言われております。また「重陽」は『菊の節句』ともいわれ、菊を用いた神事や行事が行われます。
この九月九日、上賀茂神社(賀茂別雷神社)では、【重陽神事と烏相撲】が滞りなく、無事に行われました。
陰陽の考えで、奇数は「陽」の数とされており、その中でも「九」という数字は陽の一番大きな数が重なることから「重陽」と言われております。また「重陽」は『菊の節句』ともいわれ、菊を用いた神事や行事が行われます。
この九月九日、上賀茂神社(賀茂別雷神社)では、【重陽神事と烏相撲】が滞りなく、無事に行われました。
この『烏相撲』は、初代天皇であります神武天皇の東征の折に、上賀茂神社の御祭神の祖父であられる賀茂建角身命が「八咫烏」となられて、先導を行われ、大きな功績をされた伝説と、五穀豊穣と深く関わる相撲奉納が併せて行われるようになったと考えられています。
この神事では、賀茂祭で務められる斎王代さんも参列をなされます。定刻、神職・伶人と共に斎王代が参列し、土舎で祓いの儀式が行われ、本殿へと参進されました。そして、本殿で神事が行われました。本殿祭では、烏相撲に参加をする子供達も参列をします。
写真は、斎王代が玉橋を渡っておられる様子です。こちらは、神事に奉職する者しか渡る事は出来ません。厳粛な神事におきまして、斎王代が表立って、御覧になられるのは、賀茂祭以来となります。
この「重陽神事」は先ほども綴りましたとおり、『菊の節句』でもある為、宮中では菊酒で祝ったり、菊の露で身を拭うなどを行っていた事も知られています。
【烏相撲】は、上賀茂神社独特の作法を有しております。細殿には、斎王代に着座し、細殿の南庭である立砂前に土俵が作られており、両ぎわには禰宜方・祝方にわかれて着座して、神事が始まります。
まずは、双方の神職が交互に、我が方に勝利を、という思いの呪いである地取りという作法を土俵上で行います。そして、双方の神職により、土俵上で相撲に取り組む子供達の名が書かれた符を読み上げ、小さな木に挟み、斎王代に献じ、斎王代はその符を確認します。
次に、烏帽子に白い装束を着た刀祢が、東西の帳舎から弓矢・太刀・扇を持って、交互に横に飛び跳ねながら、立砂に立て掛けて、最後にその前に着座します。座した刀祢は扇を煽りながら、交互に「カーカーカー」と三々九度烏鳴きを行います。そして、この作法が終わると、また横飛びをしながら、帳舎へと戻っていかれます。
刀祢が着座すると、祢宜方から行司の先導のもと、子供たちが立砂を三回廻ります。双方が廻った後、いよいよ子供達の取り組みが行われます。
子供達の取り組みが始まると、呼ばれた子供たちは大きな返事をして土俵へ上り、保護者のみなさんや参拝者が声援を送る中、どの子供たちも善戦の取り組みを披露してくれました。この伝統行事は京都市登録無形民俗文化財の指定を受けており、多くの人々によって支えられて、上賀茂社独特の文化を今に伝えておられます。
斎王代もその様子を興味深く御覧になられ、賀茂の伝統文化を感じておられました。
Posted by 一匹狼★NOB at 22:12│Comments(0)
│神社
この記事へのトラックバック
なぜ日本人は3や7が好きなんでしょうか?なぜ日本人は3や7が好きなんでしょうか?こんにちは、ふと買い物のレジで日本人って3や7が好きだなって思いました。これはパチンコ会社...
9月9日 重陽【芸能エンタの神様】at 2007年09月11日 03:55
和装振興を図る園遊会「2007西陣きもの・帯フェスティバル」(西陣織物産地問屋協同組合主催)が3日、京都市北区の上賀茂神社で行われました。優雅な着物姿の市民が境内を行き交...
上賀茂神社で園遊会【京都日記~独り言~】at 2007年11月03日 22:57